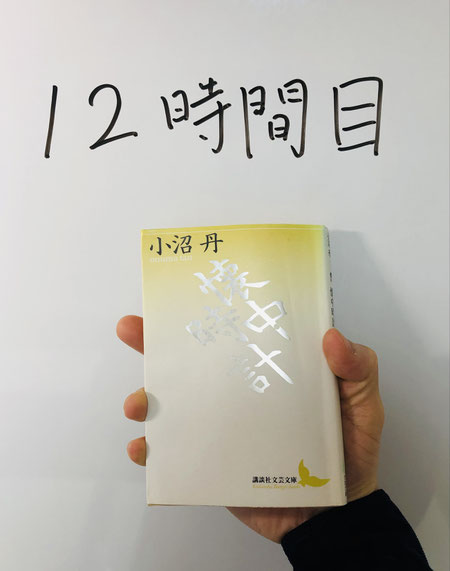
コロナウイルスを呪う今日この頃、皆さま、お元気ですか。私は、陰鬱です。
桜の花は早々に散りました。これはいかにも桜らしい身の振り方、と思いました。旧時代的言い様ですが、文字通り、「花と散った」かのようです。潔く。
去年の緊急事態宣言下、「コロナで密を作らないように」と、来客が見込まれる全国各地の観光農園、フラワーパーク等々で、チューリップが、切断、廃棄された、あの痛々しい光景がありましたが、今年はぎりぎり、緊急事態宣言と緊急事態宣言のはざまで、花弁を切られずに済んだ、ということでしょうか。あるいは、切られたものもあったのだろうか。
人間が、しょせん人間を呼びこむため、植えられたのだから、とはいえ、花は美しい、と思わないこともないこの私にも、その記事は、殺害現場の写真を目にしたような衝撃を受けました。
「来るな、と言っても、快楽主義者は来る。ならば、すべて刈り取っちまえ」
そんな命令をする人を、その野太い声を、私は瞬時憎んだものでしたが、きっと、号令をかけた人も、悔いの残る決断であったろうし、実地で、花びらを刈っていく、農園や生育係の方の、流した無念の涙は、「待てよ。これは、あまりにエゴイスティックな涙ではないか」と自問自答しながら、ひややかに乾いたことだろう、と思われ、だから加藤めがどうした、というと、つらく、せめて、いやな呪詛を口にしたい思いでいっぱいです。
加担した人たちの胸に、以降起こり立つ、すべての感興が、「どうせ」と、白々しくなるような、また、過去せっかく味わった人生の輝きを、その価値を、自らあざけって、つばして、すべてなかったことにするような、ひどい傷が刻まれたのは、果たしてよかったのか。
まったく、憂鬱でなりません。
「ばかな……」
ため息交じりに、何度口にしたことか。
いくら連呼しても、まだ足りない。
「人間なら、まずは人間を信じないのか」とも言いたい。
「人間なら、まずは人間を信じてみろよ。ウイルスの側に立つのかよ。理知的であることと、情緒的であることの両立を諦めるのか。そんなわけないだろう。君はつらいんだよ。それを素直に話してくれよ。ありがとう、俺なんだか嬉しいよ。みんなで泣こうじゃないか。この苦しみを、いったん、分かち合おうじゃないか。まずその説教みたいなのはやめにして、知事、大臣、みんなで、24時間テレビで、24時間泣き合おうよ。ずっと耐えている子どもたちにマスクじゃなくて金メダル配ってよ。とか言って、そんなものはまあいいから。金メダル級の笑いと涙を。さんちゃん、たけちゃん、タモリさん、みんなで志村けん追悼から始めませんか。再現ドラマではなく、泣きながら笑えるコントをしませんか。経営者の皆さん、心を語り合いませんか。死ぬ間際に、『アイラブユー!』って叫ぶ、あの欧米の習慣、やめませんか。あの『アイラブユー!』が聞こえたら、たちまち、もう自分は終わりなんだ、とわかる、それが怖くて。飛行機、非常時の酸素マスクが出てくるのが怖くて、いたるところから、『アイラブユー!』が聞こえてきそうで、怖くて怖くて」
緊急事態にもある、幸せな瞬間ベスト3。加藤のケース。
第3位。
「洗濯物を眺めながら、淹れたてのコーヒーをカップに注いだとき」
いまこれをタイピングしている間も、思い出すだにうれしくて、にやにやしてしまいました。よく晴れた朝は格別。さて朝刊でも開くか、という、心に余裕ができたからこその瞬間です。
第2位。
「土曜の夜にビールをグラスに注いだとき」
けっきょく、これ。日常生活、結局、これにかなう幸福感は、なかなかない。注ぎながら毎回、有森裕子さんの名言を悪用して、「今週も自分で自分をほめたいと思う」を繰り返して懲りません。
これを挙げる私、我ながら、罪のない男だな、と、泣けてきます。「自分で自分を罪のない男だと思う」。生活者の最後の砦で、せめて、これだけは奪わないでほしいものです。
そして、ついに、
緊急事態にもある、幸せな瞬間ベスト3、
輝ける第1位は……
「帰宅後、妻に話を聞いてもらっているとき」
妻に話す話なんて、大した話なんてないのです。
芸能人のゴシップ、他人の悪口や耳に挟んだ近所の噂話が大半で、他に何かあったとしても、帰宅時うんこを踏んで腹が立った、とか、うんこを漏らしそうになって焦った、うんこって臭いよね、といったような、他愛もない話。脳に直接口をつけて喋らせたように、節操なく、拙者はべらべらと垂れ流すわけです。
しかも、頷きの声が聞こえて来なかったり、いかにも傾聴の態度からかけ離れた様子だと、癇癪を起す始末。食事の用意でキッチンに隠れでもしたら、横に並んで、やります。
押しつけがましく、あつくるしく、彼女には申し訳無いわけですが。
しかし、これがないと、拙者、駄目なんです。
たまには、「帰りが遅くなるから、寝てしまってください」と連絡をしたりします。どうしても、帰宅が23時を超えることも、時にはあります。幼い子どももいる、というのもあり、そういう場合には、苦渋の決断を下し、「どうぞ寝てください」と伝える。
帰ると、もちろん、そのようになっている。机上にはラップがかけられた食事が用意されてあって、各々、電子レンジで温めなおして、……ま、いいや、どうせ拙者ひとりだから、話し相手がいなくては、精神的に味気ないのは決まっているんだよね、と、つぶやきシロー風に億劫がって、冷めたままの煮物など、むさぼるように食べたりします。この後の食器洗いでは、高確率で皿を割ることになるのだが。
翌朝。
溜まりに溜まった「妻に聞いてもらいたい話」を抱えて目を覚ますと、拙者、もう止まりません。
まず、聴き手である妻の取り合い。
ライバルは息子です。拙者が喋ろうとすると、愚息ったら、母ちゃんが独り占めされるのがいやなのでしょう、オディプス・コンプレックスよろしく、負けじと「トイストーリーが」だとか、「おばけが」だとか、「大洗のイルカが」だとか、またべらべらと喋る。声がやたらでかいので、拙者もつい声を張り上げて、「拙者の、拙者の、拙者の話を聞け~」、男2人が大変騒がしい。
息子の口をふさぐべく「今、お前さんのおやじが話す番だろう」と、拙者もむきになって怒ったりするのですが、ライバルもまた手ごわい。
「こら!」だとか「シー、だ!」だとか、闘志剥き出しで対抗してくるから、拙者も不機嫌になって、取っ組み合いの喧嘩、……というわけにはいかない。
仕方なく声を落として、洗濯物を回しに、その場を離れる。
洗濯物はいい。なにせ、裏切らない。拙者を。
回せば、浄化され、干せば、乾く。
洗濯物の回転になだめられていたら、ふと、
「妻が死んだら、どうなってしまうのだろうか」
と思う。
ずしり、と深刻な危機感が胸にのしかかってくる。
小沼丹は、妻の死後、その死を小説に書こうと思った。さらに、この頃から、空想の作り物を書くのではなく、今後は自分の身辺のことだけを題材にしよう、という心境の変化があった。
そうして書かれたのが「黒と白の猫」。
執筆の経緯は、「懐中時計」巻末にある、「著者から読者へ」に詳しいが、はじめは、自らをモデルにした人物を、「僕」という一人称で書こうとしていたのだが、「べたべたくっつくものが顔を出し」、書きあぐねていた。そこへ、「大寺さん」という人称を発見し、用いることで、小説を書くことができたという。
「小沼」ではなく、「大寺」でもない。「大寺さん」。
「〇〇さん」と、他人行儀に、しかし少し親しみを込めて、自らを呼称して、絶妙な位置に遠ざけたのは、なんと切実で、なんと仕組まれた発明だろう。著者に言わせると「どこから出て来たのか、これは作者にもさっぱり判らない」とのことだが。
飄々とした猫の登場もあって、「妻の死」という深刻な題材であっても、さほど深刻にならず、過剰に飾らず、かといって、冷淡になりすぎることなく、描かれていく。
コロナ禍。国難。パンデミック。緊急事態。
「大寺さん」の視点をヒントに、どうにか、このどん詰まり感、切り抜けていきたいから、洗濯物を干し、コーヒーを注ぎ、ビールを注ぎ、妻を奪い合い、本を読んでいきたい。
